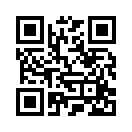2008年11月12日
ここまでの反省、電源編
電気に関しても、一般性と特殊性の差別化がなかなか難しい。
プロオーディオは、使用する機材の関係上、アメリカ製、ヨーロッパ製、日本製が混在するのが普通。
電圧はアメリカが117V.ヨーロッパが240V.日本が100V。最近の機材はユニバーサル電源や切り替え式の電圧セレクトが標準なので、ひと昔前よりは電圧問題は少ない。
それでもアース付きの117Vは必需品。むしろ117Vが標準といってもいいくらいだ。極まれに、200Vを用意することもある(イギリス製の大型コンソール等)。
第一案を見せてもらった時は、コンセントが全て壁にあってピットやラック回りに何も無かった。しかもほとんど100V仕様。さすがに不安になった。でもこれは単なる説明不足と言う事で‥‥
もうひとつ大事なことがある。それは『クリーン電源』
このクリーン電源に関してはなかなかうまく理解してもらえない。電源の波形が歪んだとき、オーディオ信号もそれにつられて、なまってしまう現象だが、ジーとかブーとかのハムノイズが出る訳ではないので、一般の電気工事のやり方では、いろいろと配慮の欠けた状態になってしまう。
主な原因は一般家電等から出るノイズや揺れる電圧、誘導電波‥‥電気容量等いろいろある。
今回は、シンプルに生活用の電源(雑電源)とオーディオ専用電源を大幹で分ける事を基本に、必要に応じてトランスを使うやり方にするつもり。‥‥でも業者さんは興味なさそうだった(笑)
オーディオにとって質の高い電源はこれ以外にもコンセント、ケーブル等、理にかなった物から迷信めいたものまで、際限ないくらいあるが、最低限、一般の家電から出るノイズを分離できれば、それなりのクリーンさをキープ出来ると考えている。
そうそう、オーディオ専用の電気容量は100アンペアにした。単純計算では多少の余裕も見込んである。
問題は、私以上に電源と音とノイズの関係を考えている業者さんがいない事。自分の適当な発言もそのまま形になってしまう。(こわっ)
自分の考え方は理論よりも、経験から学んだ事の方が多いため、ときどき『説明出来ないことを言ってしまう』
これが誤解されると、またとんでもない事が‥‥
照明に関しても同じ事が言える。
スタジオの中で、どんな楽器がどの場所で何処を向いて演奏するのかイメージしていないため譜面台に必要な光量の目安が大雑把だったり、安易に蛍光灯を使ってノイズ対策がされてなかったり‥‥。修正出来るのでまだ詰めていないが、全体的にこの種の問題を抱えながら進行中。
電源は全体の容量と振り分けに無理が無ければ、建築と違い、後での対応幅もあるので、多少気楽に考えている。
それでも普段なかなか出来ないことで、今回やれることもある。アースがまさにそんな感じ。
東浜は埋め立て地なので基礎工事前に、地中深くパイルを打ち込む様に指定されている。スタジオ付近では、地下12m前後が岩盤になっているので、パイル打ちの時、ついでにアース線も打ち込んでみる。
結果は音を出してみないと判らないが、数少ないアドバンテージのひとつ
プロオーディオは、使用する機材の関係上、アメリカ製、ヨーロッパ製、日本製が混在するのが普通。
電圧はアメリカが117V.ヨーロッパが240V.日本が100V。最近の機材はユニバーサル電源や切り替え式の電圧セレクトが標準なので、ひと昔前よりは電圧問題は少ない。
それでもアース付きの117Vは必需品。むしろ117Vが標準といってもいいくらいだ。極まれに、200Vを用意することもある(イギリス製の大型コンソール等)。
第一案を見せてもらった時は、コンセントが全て壁にあってピットやラック回りに何も無かった。しかもほとんど100V仕様。さすがに不安になった。でもこれは単なる説明不足と言う事で‥‥
もうひとつ大事なことがある。それは『クリーン電源』
このクリーン電源に関してはなかなかうまく理解してもらえない。電源の波形が歪んだとき、オーディオ信号もそれにつられて、なまってしまう現象だが、ジーとかブーとかのハムノイズが出る訳ではないので、一般の電気工事のやり方では、いろいろと配慮の欠けた状態になってしまう。
主な原因は一般家電等から出るノイズや揺れる電圧、誘導電波‥‥電気容量等いろいろある。
今回は、シンプルに生活用の電源(雑電源)とオーディオ専用電源を大幹で分ける事を基本に、必要に応じてトランスを使うやり方にするつもり。‥‥でも業者さんは興味なさそうだった(笑)
オーディオにとって質の高い電源はこれ以外にもコンセント、ケーブル等、理にかなった物から迷信めいたものまで、際限ないくらいあるが、最低限、一般の家電から出るノイズを分離できれば、それなりのクリーンさをキープ出来ると考えている。
そうそう、オーディオ専用の電気容量は100アンペアにした。単純計算では多少の余裕も見込んである。
問題は、私以上に電源と音とノイズの関係を考えている業者さんがいない事。自分の適当な発言もそのまま形になってしまう。(こわっ)
自分の考え方は理論よりも、経験から学んだ事の方が多いため、ときどき『説明出来ないことを言ってしまう』
これが誤解されると、またとんでもない事が‥‥
照明に関しても同じ事が言える。
スタジオの中で、どんな楽器がどの場所で何処を向いて演奏するのかイメージしていないため譜面台に必要な光量の目安が大雑把だったり、安易に蛍光灯を使ってノイズ対策がされてなかったり‥‥。修正出来るのでまだ詰めていないが、全体的にこの種の問題を抱えながら進行中。
電源は全体の容量と振り分けに無理が無ければ、建築と違い、後での対応幅もあるので、多少気楽に考えている。
それでも普段なかなか出来ないことで、今回やれることもある。アースがまさにそんな感じ。
東浜は埋め立て地なので基礎工事前に、地中深くパイルを打ち込む様に指定されている。スタジオ付近では、地下12m前後が岩盤になっているので、パイル打ちの時、ついでにアース線も打ち込んでみる。
結果は音を出してみないと判らないが、数少ないアドバンテージのひとつ

Posted by iguchi susumu at 01:50│Comments(0)
│プラニングから工事まで